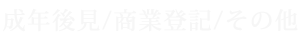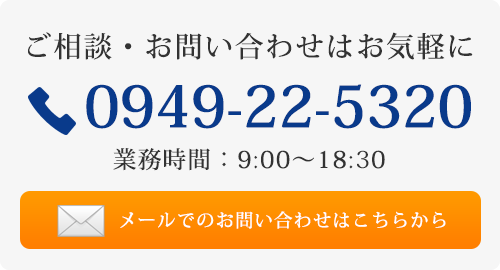成年後見
成年後見とは

成年後見制度とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の判断能力の不十分な成年者を保護するための制度のことです。成年後見人がつき、不動産や預貯金などの財産の管理、介護施設への入所契約、遺産分割の協議等を行います。また、不利益な契約であってもよく判断出来ないまま契約を結んでしまうため、認知症高齢者を狙う悪徳商法も多くあります。そういった際に売買の取り消しを行う事もあります。
成年後見は、このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するための精度です。
そしてこの成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度
法定後見人制度とは、認知症等により判断能力が衰えている場合に、親族等が家庭裁判所に申立て、家庭裁判所が後見人等の援助者を選任する制度のことです。この法定後見制度は,本人の判断能力の程度によって、「後見」「保佐」「補助」の3段階に分かれています。
後見とは

後見は、日常的に必要な買物も自分では出来ず、誰かに代わって貰う必要がある等、本人の判断能力がほとんど無い場合に適応されます。自分自身で財産の管理や処分が出来ないため、本人の援助者として成年後見人が家庭裁判所によって選任されます。
成年後見人には、原則として下記の権限が与えられます。
- 財産管理権と代理権
- 被後見人の行った行為の取消権
資産の管理や、悪徳商法により契約してしまった物を取り消したり出来ます。後見が開始すると、本人は選挙権を喪失し、会社の役員や一定の職業の地位を失う等の制限が発生します。
保佐とは

保佐は、日常的な買物程度は自分自身の判断で出来るものの、援助が無ければ不動産の売買や金銭の貸し借り等の財産管理が援助なしには判断出来ないような、本人の判断能力が著しく不十分な場合に適応されます。本人の援助者として保佐人が家庭裁判所によって選任されます。
保佐人には、原則として下記の権限が与えられます。
- 被保佐人の重要な財産行為(不動産の売却や遺産分割等)に同意権
- 家庭裁判所と被保佐人が認めた特定の事項について代理権。
※被保佐人が、保佐人の同意を得ずに重要な財産行為を行った場合には、後で取り消すことができます。 保佐が開始すると、本人は会社の役員や一定の職業の地位を失う等の制限が発生します。
補助とは

補助は、重要な財産行為は自分で判断出来る場合もあるが、出来るかどうか危惧があるので、本人の利益のために援助があった方が良いような、本人の判断能力が不十分場合になされるものです。被補助人の援助者として補助人が家庭裁判所によって選任されます。
補助人には、原則として下記の権限が与えられます。
- 家庭裁判所と被補助人が認めた重要な財産行為を、被補助人が行う際に同意する
- 家庭裁判所と被補助人が認めた特定の事項について、被補助人を代理する。
※被補助人が補助人の同意を得ずに財産行為を行った場合には、後で取り消すことができます。
任意後見制度

任意後見制度とは、本人の判断能力があるうちに、将来的に認知症等によって判断能力が不十分になると想定して、将来自分の任意後見人になってもらいたい方と、後見事務(代理権)の内容を公正証書による任意後見契約によってあらかじめ決めておく制度のことです。
任意後見契約の委任者(本人)の判断能力が低下した段階で、原則として本人の同意を得て、家庭裁判所に任意後見人の仕事を監督する任意後見監督人を選任して貰い、任意後見人の事務が開始されます。
今は問題なく何事も判断出来ているが、将来自分が認知症になるかもしれないという不安をお持ちの方が、将来を見越して事前に後見人を選んでおく際に利用される制度です。
※現時点では判断能力に問題のない方のみ利用可能です。
任意後見制度の流れ

家庭裁判所と被補助人が認めた重要な財産行為を、被補助人が行う際に同意する。

痴呆、認知症の症状が現れはじめる。

家庭裁判所に申し立てる。

任意後見人が任意後見契約で定められた事務(財産の管理等)を行う。
その他
法律相談